

新潟市の大学で高齢者とペットの飼育をテーマにした講義が行われた。飼い主の死亡などにより、突然ペットが取り残されてしまうことを防ぐために必要なこととは何か…学生たちが学んだ。
■多頭飼育崩壊の現場で「不妊・去勢手術を拒否された」
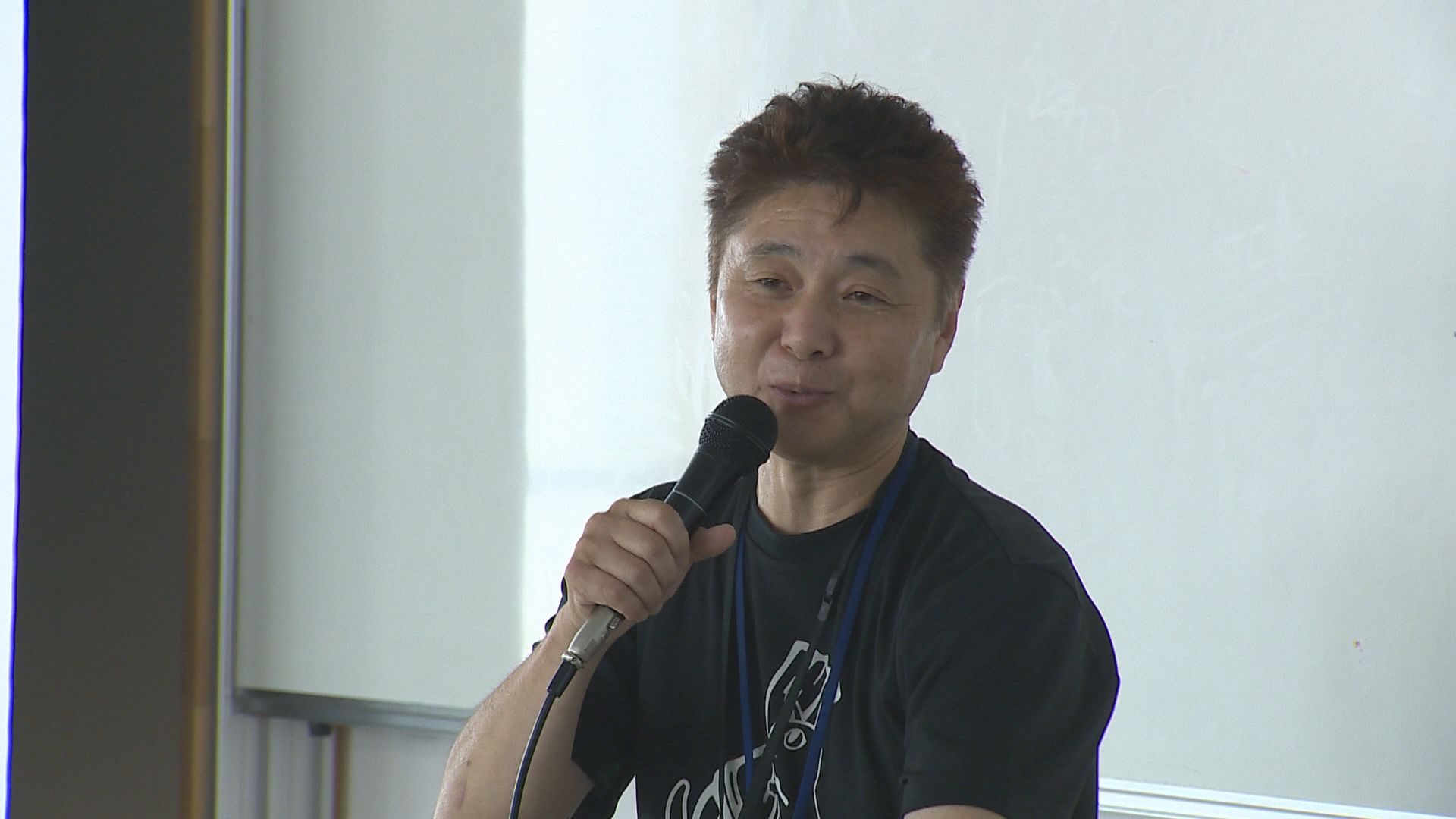
新潟市北区の新潟医療福祉大学で行われた『高齢者とペット飼育』をテーマにした講義。
チーム医療・ケアについて実践的に学ぶ連携総合ゼミの一環として行われたもので、医療や福祉などの業種を志す学生などが参加した。
講義ではまず、新潟動物愛護センターの登坂友一所長からペット飼育全般の課題となっている多頭飼育崩壊の現状が説明された。
「(現場に行き)私が見たときに猫が10匹ほどいると思った。すぐに不妊・去勢手術をしないと、また増えますよと。増えてかわいそうな子が出てくるから去勢手術しましょうと言っても拒否された」
多頭飼育崩壊現場などでとられる取り組みに“TNR”がある。
TNRとは『Trap=捕獲し、Neuter=不妊去勢手術を行い、Return=元の場所に戻す』取り組み。TNR後の猫は里親探しに出される場合と、地域猫として元いた場所に戻るケースがある。
こうした取り組みにより、猫の増殖に歯止めをかけている。
■飼い主の生活困窮も原因に…新潟市のペット飼育問題の現状

新潟市のペット飼育問題の現状について登坂所長は次のように分析している。
2024年度の新潟市におけるTNR相談件数は江南区で5件、西蒲区で5件、北区で5件、南区で4件、秋葉区で3件、西区で2件、中央区で1件。
人口が少ない地域ほど、ペットの飼育問題を抱えていることが多いという。
高齢者層にいまだ「猫は外で飼うもの」と考える人が多いことも一因であると分析している。
また、相談者の特徴として猫の数が5~6匹では何も対応をとらないが、10匹を超えると相談してくる人が比較的多いという。
問題の根底に飼い主の生活困窮があることも珍しくない。
実際に、ペットを飼う身寄りのない高齢者が一人で亡くなり、アパートなどの室内に閉じ込められていた事案もあるという。
登坂所長はこの数日間、3匹の猫を残して孤独死した飼い主の家に通い、猫の捕獲を試みている。
飼い主が亡くなったのは8月17日。その後、不動産業者が飼い主を発見した。飼い主は生活保護受給者だった。
26日時点で2匹は捕獲が完了しているが、1匹はいまだ姿を見ることができていないという。
■愛するペットのためにも備えを「死後の準備は健康なうちに」
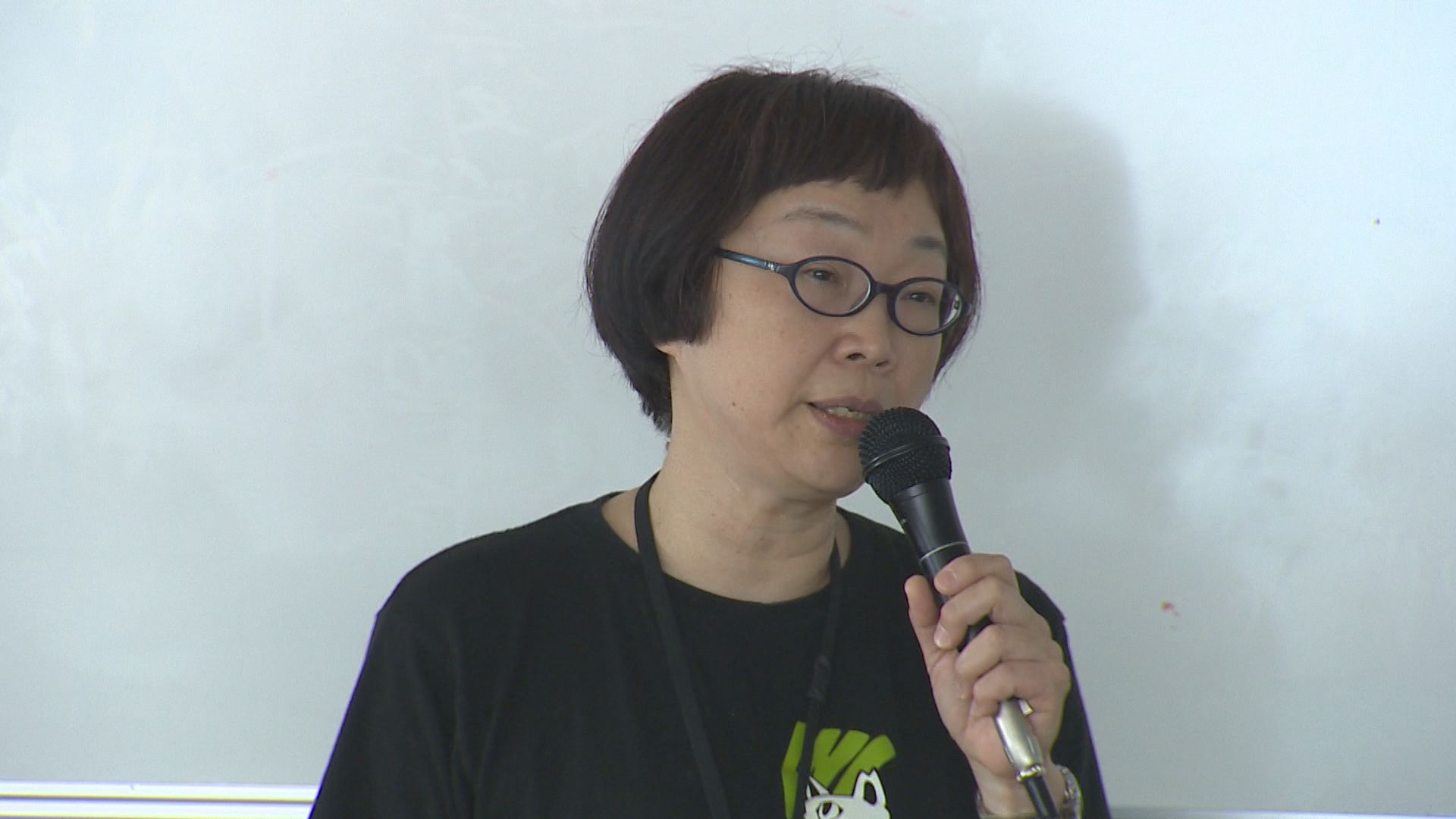
講義のもう一人の講師で、飼い主のサポートなどをする市民活動グループどうぶつがかりの三浦真美代表は、高齢の飼い主の事例を紹介し、民生委員などと連携して問題の早期の発見・解決に取り組んだ事例などを伝えた。
死を前にした飼い主と関わってきた三浦代表が話すのは、健康なうちからの準備だ。
「死に際は遺言書を書くとか、誰かに託すとか、そんなことはできない。だから死後の準備は健康なうちにしておかなければいけない」
■ペット飼育問題 “崩壊”状態になる前に自覚を

こうしたペット飼育の問題について、登坂所長は5段階に分けて説明した。
第1段階は“飼いはじめ”。第2段階は“充実期”。ここまではペットを正しく飼育できている状況だ。
そして、その状況が何らかの理由で崩れたときに「このまま飼い続けられるのだろうか」と不安になるタイミングが来る。
そして、多頭飼育崩壊などの崩壊状態に陥った時が第4段階の“崩壊”。そして第5段階は“最終局面”、すなわち飼い主の死だ。
登坂所長は「3段階目までには飼い主に気づかせ、状況の改善に取り組めることが望ましい」と話す。
■ペットを飼う前に…“5つの点”で判断を

登坂所長はペットを飼う前に判断すべき点は5つあるという。
1つ目は“経済力”。経済力について、犬は年間18万円、猫であれば7万円、平均でかかるといわれている。自身がペットを飼育するのに十分な経済状態であるか検討する必要がある。
2つ目は“飼い主そのものの問題”。飼い主の持病など、自身がこの先もペットを飼い続けられる見込みが立つのかどうかを見極める必要がある。
3つ目は“家族構成”。飼い主の死去があった場合、最終的に誰がそのペットの面倒を見るのかについて見込みが立つ家族構成なのかどうか。
4つ目は“住宅”について。自身の住宅がペットを飼育するのに適した環境であるかどうか。
5つ目は“犬・猫への知識”。犬や猫の習性や飼育において留意すべき点など、しっかりと知識を有しているのかどうか確認するのも飼い主の責任の一つだ。
■“高齢者とペット飼育”について学んだ学生たち「動物にも支援を」
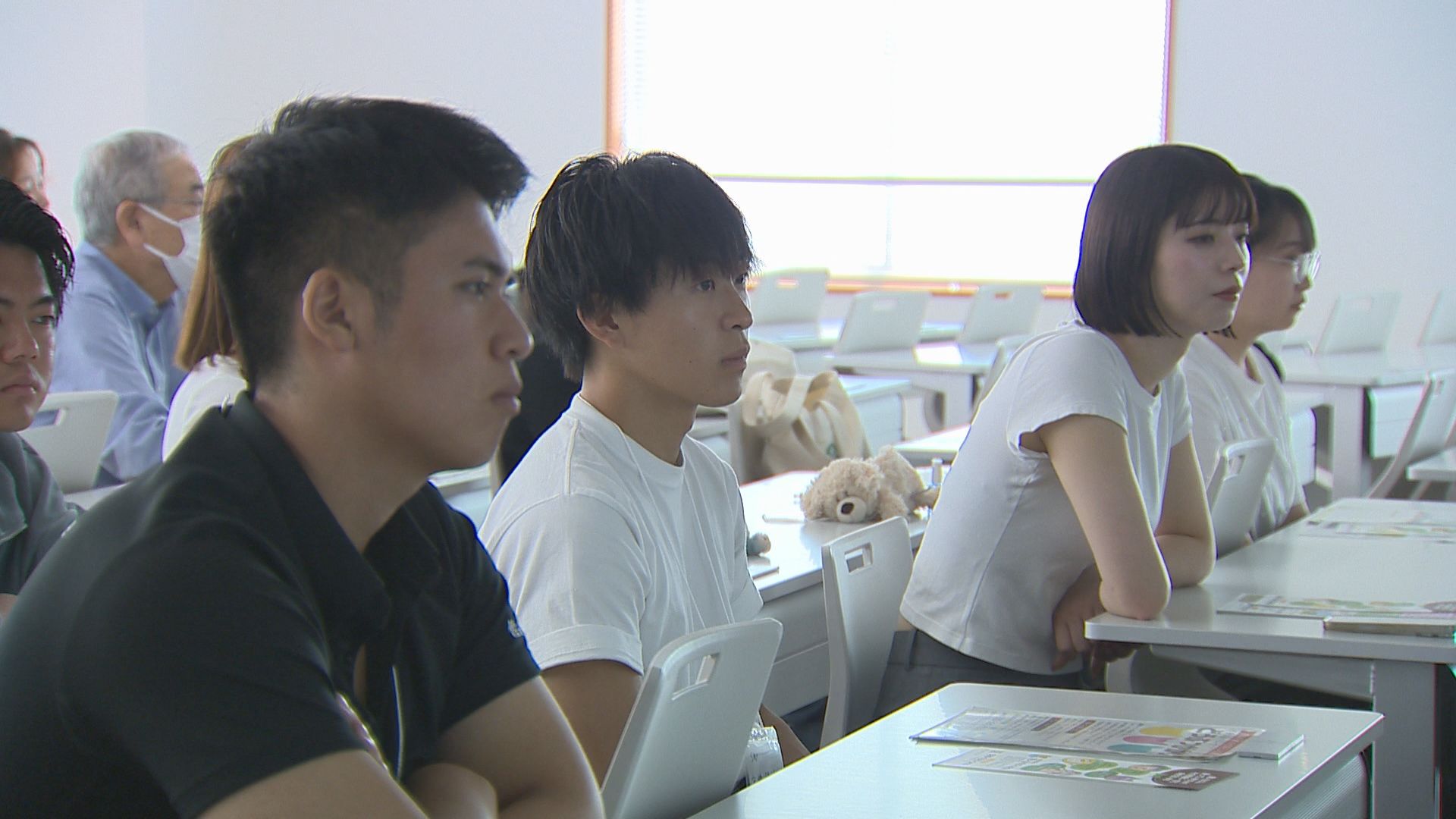
受講した学生たちからは「人間だけではなくて、動物にも支援をしていかなければいけないと今回の話を聞いて強く思った」「家の環境を見た中でペットがいることやペットの状況にも気づけたら良い」といった声が聞かれた。
登坂所長は「少なくとも地域コミュニティーが昔よりもなくなってきている。変化を察知してくれる人がいればここまで行かなくてすむのかなと思っている。きょうの話が福祉系で働くことを志す皆さんの何かのヒントになればと思う」とメッセージを送った。
(NST新潟総合テレビ)
最終更新日:Sun, 31 Aug 2025 18:00:00 +0900

