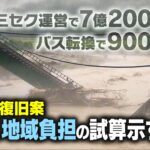スマートフォンやタブレットなどの普及から、物や画面を近くで見る機会が確実に増えている今の時代。こうしたライフスタイルの変化に伴い、今“学童の近視”が問題となっている。近視を抑制するための方法を医師に聞いた。
■増加傾向の“近視”…その要因は?

「子どもが近視になるというのは、日本だけではなくて世界的な傾向」こう話すのは、はにゅうクリニックの副院長・羽入貴子医師だ。
近視とは、正常な場合と比べて眼球の形が後ろ方向に伸びてしまい、網膜よりも前に焦点を結んでしまう状態のこと。
近くのものは鮮明に見えるのに比べ、遠くのものはぼやけてしまうといった症状が出る。
そもそも近視の要因はどのようなものなのか。
羽入医師は「両親が近視、もしくは片方の親が近視な場合。あとは環境因子、赤ちゃんの頃から近い物ばかり見ているとか、屋外に行かないとか、そういうことは近視が発症する大きな要因になる」と話す。
目の負担が増えてしまう近視は進行すると、将来的に緑内障や網膜剥離などの目の病気にかかりやすくなるのも事実だ。
■近視防ぐには…“距離”は長く“時間”は短く
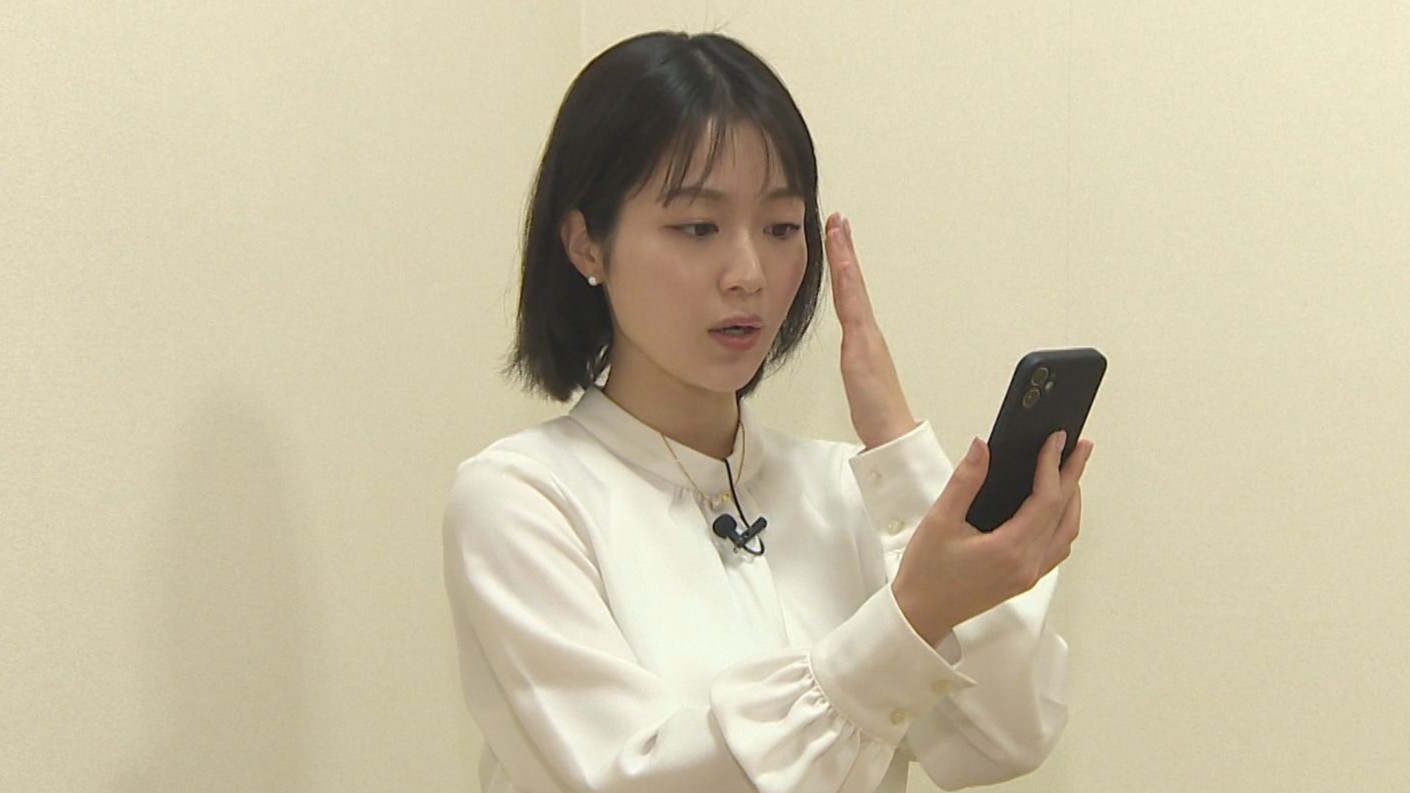
近視を防いだり、進行を遅らせるためには、適切な距離で物を見る必要がある。
最低でもデジタルデバイスより30cm、教科書や本は30~35cm、テレビは2~3m離れて見ることが重要だ。
ほかにも「視距離という要因と持続時間、総時間が関係していて、持続時間というのが近視の進行にかなり関係していると言われている。30分以上持続すると、近視の頻度が上がる」と羽入医師は指摘。
物を見る“距離”は長く、“時間”は短くすることが近視を抑制する上で重要だ。
■“太陽の光”も近視の抑制に

さらに近視の抑制に効果的なものが、太陽の光だという。
「太陽の光の照度と太陽の光の波長の中に近視を抑制する因子が入っているのではないかと言われている」
太陽が放つ光には、近視を抑制する効果があるため、幼い頃から屋外での活動を増やすことが大切になる。
「屋外活動には色んな因子があって、例えば運動とか、近くを見ずに遠くを見る、色んな因子が入っているのではないかと言われている。必ずしも直射日光に当たらなくていい、日陰で十分なので、屋外で目の中に光を取り入れるというのは大事」
ただ、太陽を直接見ると目を痛めてしまうので注意が必要だ。
■デジタルデバイスは「大きめのものを」

そして、今や生活の中で欠かせないものとなっているデジタルデバイスを使う際は、使い方を工夫するだけでも近視の抑制につながると羽入医師は話す。
「デジタルデバイスに関しては、小さいものはできるだけ避けて、例えばゲームをやるにしてもゲームの内容をテレビに映してみれば、大きくなって少し離れて見ることもできる。今、学校でもタブレットを使って勉強していると思うが、なるべく大きめのタブレットにして、30cmは距離を取る、30分見たら遠くを20秒以上は見て、目を休めるようにするということ」
屋外での活動を通し、太陽の光を積極的に浴びること、そして意識的に物を見る“距離”と“時間”を調節することが近視を抑制する効果につながる。
近視を発症する年齢が低いほど将来的に目の病気になる確率が上がるため、注意が必要だ。
(NST新潟総合テレビ)
最終更新日:Sun, 06 Apr 2025 10:00:00 +0900